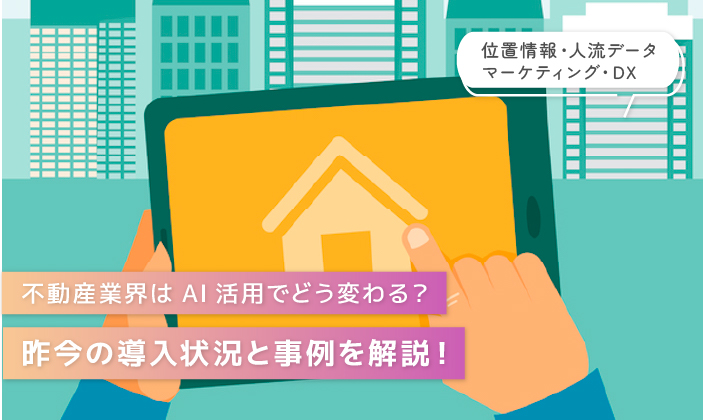ビーコンを使ったマーケティングとは?ほかの通信機器との違いと活用方法

ビーコンといえば、遭難者の捜索、最近は紛失防止タグのイメージが強いかもしれません。
しかし現在は、ビーコンの信号を発信する機器が広く普及し、さまざまなところで利用されています。特に、精度の高い位置情報を利用したマーケティング分野での利用が増えており、実店舗の集客に大きな効果を上げているのです。ビーコンの概要と新しい活用方法について紹介します。
ビーコンとは

ビーコン(Beacon)とは、Bluetoothを使った情報通信の方法や、その信号を発信できる端末(デバイス)のことです。スマートフォンのようにビーコンの信号を受信し、位置を特定できる受信端末とセットで使われます。
ビーコンとは、もともとは灯台やのろしなど、何かを誘導したり、信号を送ったりするものを指す言葉です。現在ではその意味が転じて、情報通信技術やその端末を指すことが多く、
- ナビゲーション
- 遭難信号
- 紛失防止
- 見守り
- マーケティング
などのさまざまな用途で使われています。暮らしのなかで活用されているもののなかには移動可能な端末もありますが、企業のマーケティング用途で使われるビーコンの受信端末は、建物に固定されているものが主流となっています。
ビーコンの仕組み
ビーコンを用いて位置を特定し、情報を受信する仕組みは次のとおりです。
- ビーコンは、常に一定の時間間隔で、近距離に信号を発しています。
- 受信端末から半径約数センチメートル~数十メートル程度の範囲内にビーコンの端末が存在すると、受信端末がそれを感知し、ビーコンの位置情報をサーバーに送信します。
ビーコンが普及してきた背景
ビーコン自体は以前から交通情報や遭難救助などで使われていましたが、ビーコンの受信端末として使えるスマートフォンが普及したことで、信号を発信する端末もたくさん設置されるようになりました。
スマートフォンは基本的にBluetooth、多くはBLE 規格(Bluetooth Low Energy)のBluetoothを搭載しています。消費電力が小さく長時間の利用が可能なため、受信端末として幅広い用途で活用することができます。
ビーコンの特徴と、ほかの通信方法との違い

ビーコンと同じように、位置情報の測定に用いることのできる技術には、GPS(Global Positioning System、全地球測位システム)やWi-Fiなどがあります。
*位置情報を活用したマーケティング手法については、「位置情報マーケティングがビジネスを加速させる!その効果と注目される理由とは?」を参照ください
ビーコンの特徴
ビーコンには次のような特徴があります。
- 信号を送信できる範囲が比較的狭い
信号を送信できる範囲が約数センチメートル~数メートルと狭い一方で、高い精度でピンポイントでの位置測定ができることが大きな特徴です。
ただし、受信端末が感知できる範囲外の場所での位置測定はできません。
また、金属や柱、壁など障害物の多い環境では精度が落ちる場合があります。
- 受信端末はそれぞれのビーコン端末の個別信号を識別して通信できる
複数のビーコン端末を同時に認識しても、信号同士が干渉しません。
この特徴と精度の高い位置測定を生かして、ユーザーの動向を詳しく知ることができます。 - 屋内や地下でも利用できる
ビーコンの信号はそれぞれの端末の個別信号を識別して通信するため、屋内や地下でも利用することができます。 - ビーコンの発信端末は電池の消費が少ない
長時間連続使用や長時間の行動記録が可能です。
ビーコンとGPSとの違い
位置測定が可能な通信には、GPSがあります。GPSは人工衛星を利用して位置を測定する仕組みです。
GPSは、身近なところではGoogle マップ、携帯電話の位置情報取得、カーナビゲーションシステム、任天堂の「ポケモンGO」などのゲーム、ラグビーやサッカーで選手の動きをトラッキングするためなどに使われています。
GPSはビーコンと比較すると、次のような違いがあります。
- GPSは全世界規模で利用できるが、衛星からの電波状況により精度が低下する場合がある
複数のGPS衛星の電波を受信する必要があるのですが、受信できるGPS衛星の数が少ないと精度が落ちてしまいます。 - GPSは衛星から大量のデータを取得できる
Bluetoothが届く数メートル範囲のみの情報のみとなるビーコンに比べて、大量のデータが取得できます - GPSは空間的精度が低い
ビーコンに使われるBluetoothの誤差は最大数メートルであるのに対し、GPSは数メートルから数十メートルの誤差が生じることもあります。 - GPSは地下では利用できないこともある
GPSは衛星からの信号を利用するため、信号が届きづらい地下や周辺に障害物(建物や壁)があると利用できないことがあります。
※GPSについては、「意外と知らないGPSの仕組みとは?位置情報を測定する仕組みから用途まで詳しく解説します!」を参照ください
ビーコンとWi-Fiとの違い
Wi-Fiは、無線によってパソコン、スマートフォン、タブレット、ゲーム機器などのさまざまな端末をインターネットに接続する情報通信技術です。端末がインターネットに接続するアクセスポイントから位置情報を取得しています。
Wi-Fiはビーコンと比較すると、次のような違いがあります。
- 空間的精度に差がある
Wi-Fiの電波は50~100メートル程度ですが、壁などの障害物で遮られるため、実際にはこれより短くなります。Wi-Fiの精度はGPSよりは高いですが、誤差が最大数メートルとされるビーコン(Bluetooth)よりは低くなります。 - 複数の電波が干渉する
Wi-Fiは信号同士が近くにあると干渉し合い不安定になります。複数のアクセスポイントが近くにあったり、近くで電子レンジなどの家電を使ったりすると、干渉して不安定になります。
なお、Wi-Fiもビーコンと同様、電池の消費は少ないため長時間利用が可能であり、アクセスポイントさえあれば屋内や地下でも利用が可能です。
ビーコンはどこで活用されているか

ビーコンは従来の利用方法で使われることも多いですが、最近では、マーケティング分野でよく活用されています。
- マーケティング・販促
実店舗では、集客や販促の手法のひとつとして、ビーコンを使ったマーケティングが行われています。- ビーコンの電波を受信した端末に対して、エリアや店舗の情報を発信する
- 店舗に近づいたら混雑状況や商品情報、お得情報やクーポンをリアルタイムに配信する
- 店舗に入ったらチェックインポイントを付与し、来店回数に応じたサービスを提供する
ビーコンはスマートフォンの位置情報を取得できるため、店内やイベントスペースに複数の受信端末を設置することで、顧客がどのように行動したかを把握することができます。そうした情報に基づいて、店舗のレイアウトを変えるなど効果的な誘導や販促が可能です。
また、スマホのアプリと組み合わせることで、顧客がアプリをインストールするとビーコンの信号を受信するたびに必要な情報を通知することができます。例えばセール・キャンペーンの最新情報や、そのエリアならではの音声ガイド、実店舗や観光地へのチェックイン、スタンプラリーなど、幅広くマーケティングに活用することができるでしょう。顧客の情報が蓄積されることで、より効果的な広告配信、情報発信が可能となります。
- 紛失防止
財布、鍵、パソコンなどの貴重品に小型のビーコンを取り付け、置き忘れや、紛失を防止します。「MAMORIO」やAppleの「AirTag」などの紛失防止デバイスが有名です。- 紛失を防止したい貴重品にビーコン端末を取り付けます。
- スマートフォンやタブレットを受信端末(親機)として登録します。
- スマートフォンにビーコンの電波が届かなくなる(置き忘れられそうになる)と、アラートが発信されて紛失を防ぎます。
- 子どもや高齢者の見守り(屋外での位置情報の可視化)
見守り対象者(子どもや高齢者)にビーコンを持たせ、位置を把握して安全確認を行います。- 見守り対象者にビーコン端末を持たせます。
ビーコン端末にはスマートフォンだけでなく、キーホルダーやお守り型などの専用端末もあります。
- 親や介護者がビーコン端末の情報を登録したスマートフォンを持っていれば、子どもや高齢者の位置情報や現在の状況を把握できます。
- また、路線バスにビーコン端末をつけることで、現在どこにいるか、次のバス停まであと何分かを把握することも可能です。
- 見守り対象者にビーコン端末を持たせます。
これらの使い方は、従来のアバランチビーコン(遭難者発見)や、VICS(道路交通情報通信システム)によるカーナビゲーションの応用です。
- モノや人の位置管理(屋内での位置情報の可視化)
位置を把握したい人やモノにビーコン端末をつけておけば、屋内でもどこにいるのかがわかります。そこで、次のような応用が可能です。- オフィスでの勤怠管理、工場やオフィスでの従業員の位置管理
- フォークリフトなど稼働する機器の位置管理
また、ユーザーの位置を把握することで、次のように場所にマッチした情報を発信できます。
- 観光地や施設内での、現在地を基準にした道案内
- 美術館や博物館の、作品ごとの音声ガイド
- テーマパークやイベント会場での、ブースごとの情報発信
- 行動分析
個別の信号を長時間追うことで、一時的な位置を把握するだけでなく、一定期間のユーザーの行動を可視化することができます。可視化したデータにもとづいて次のような情報を把握し、行動分析や人流分析が行えます。- ユーザーがどういうルートをたどったのか
- ルート内でどこにどのくらいの時間立ち寄ったのか
- どの部分で人流が滞留していたのか
最近はとくに、近接マーケティング(※)分野でのビーコンの需要が高まっています。手軽に利用でき、効果が大きく、即効性もあるため、効果を発揮しているのです。
※近接マーケティング:顧客が実際にいる場所にもとづいて行うマーケティング活動のこと。特定のエリアで配信される広告コンテンツの配信を指すこともある。
ビーコンの利用はこれからますます増える見通し
ネットショッピングが普及してから、実店舗は集客に苦労することが続いてきました。
しかし、インターネットと実店舗を組み合わせたマーケティングを行うことで、「いま近くにいる人々」を対象にした集客を行うことができます。現在のマーケティングに加えて、ビーコンをはじめとする位置情報サービスを活用し、人流データを可視化できればさらにマーケティングの効果を高められます。
位置情報やビーコンを利用したマーケティングをお考えなら、株式会社ブログウォッチャーが提供する位置情報データサービス「プロファイルパスポートSDK」をご活用ください。ビジネス価値の高い位置情報にもとづき、さまざまなマーケティングが可能です。スマートフォン向けに構築されているので、リアルタイムな集客や販促にも高い効果があります。
詳しくは、次のページをご覧ください。
位置情報サービス プロファイルパスポートSDK|株式会社ブログウォッチャー